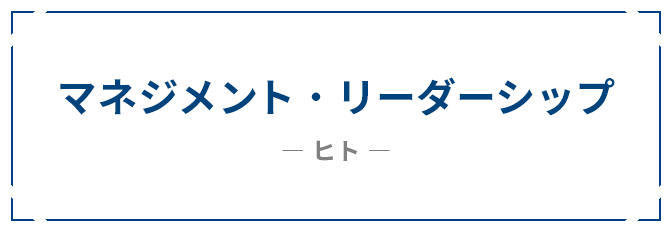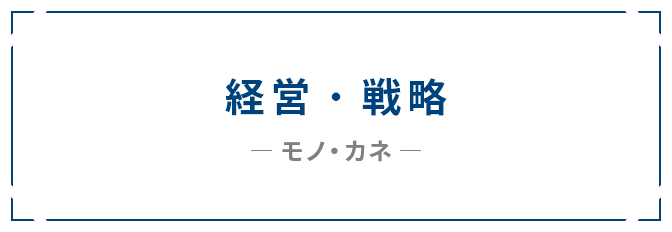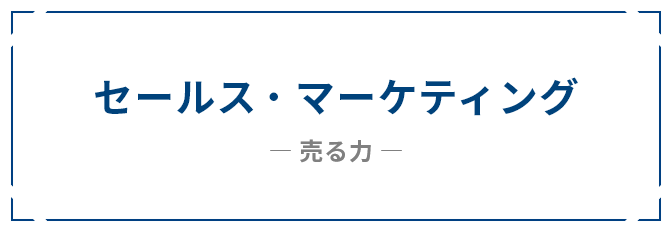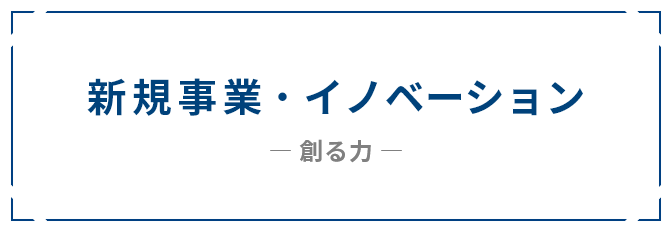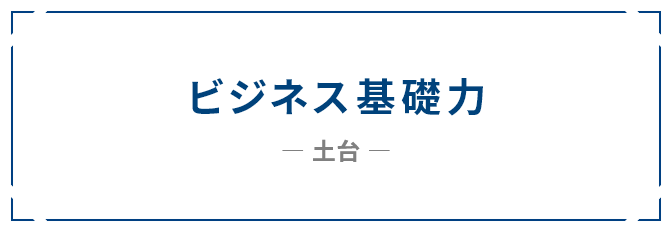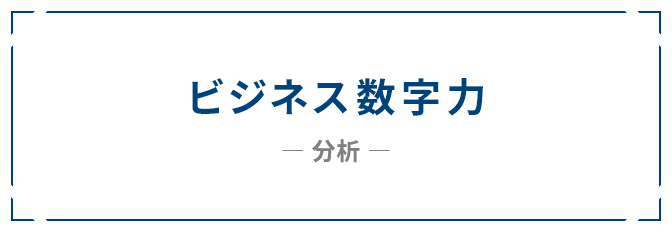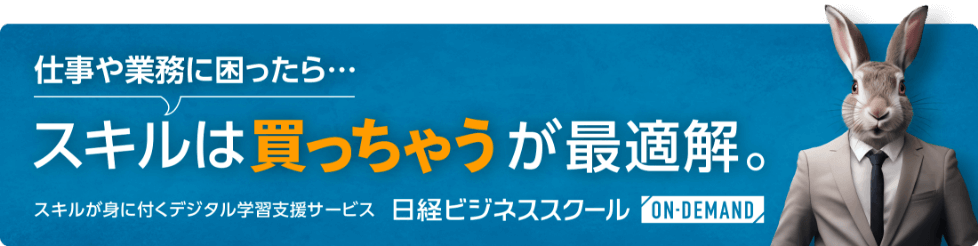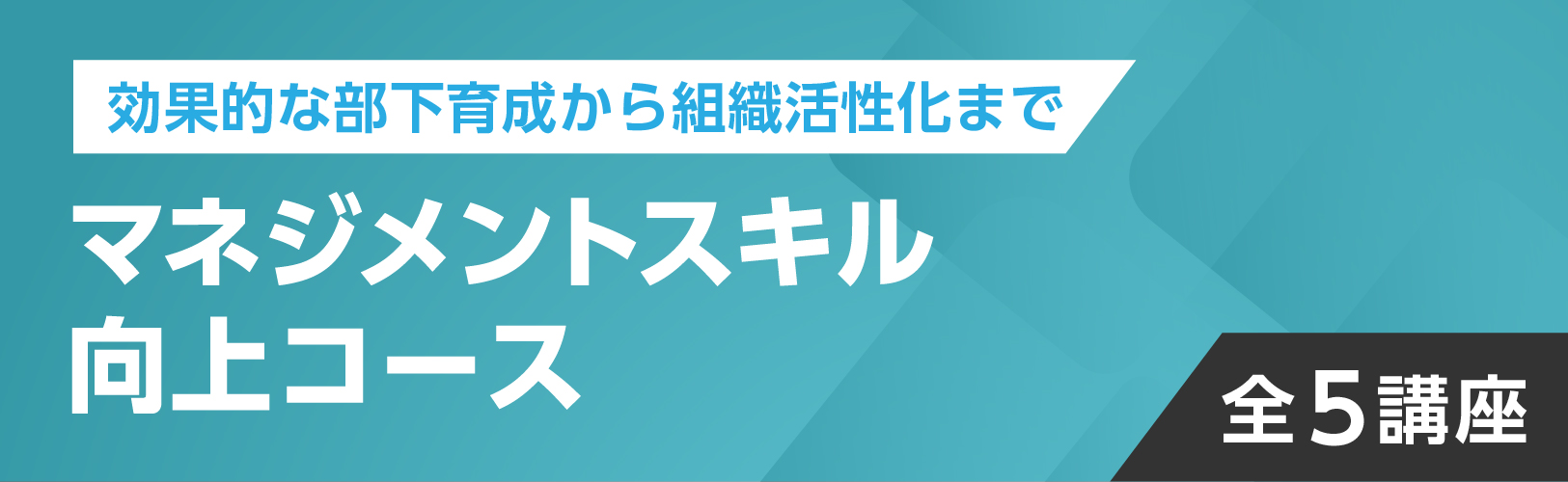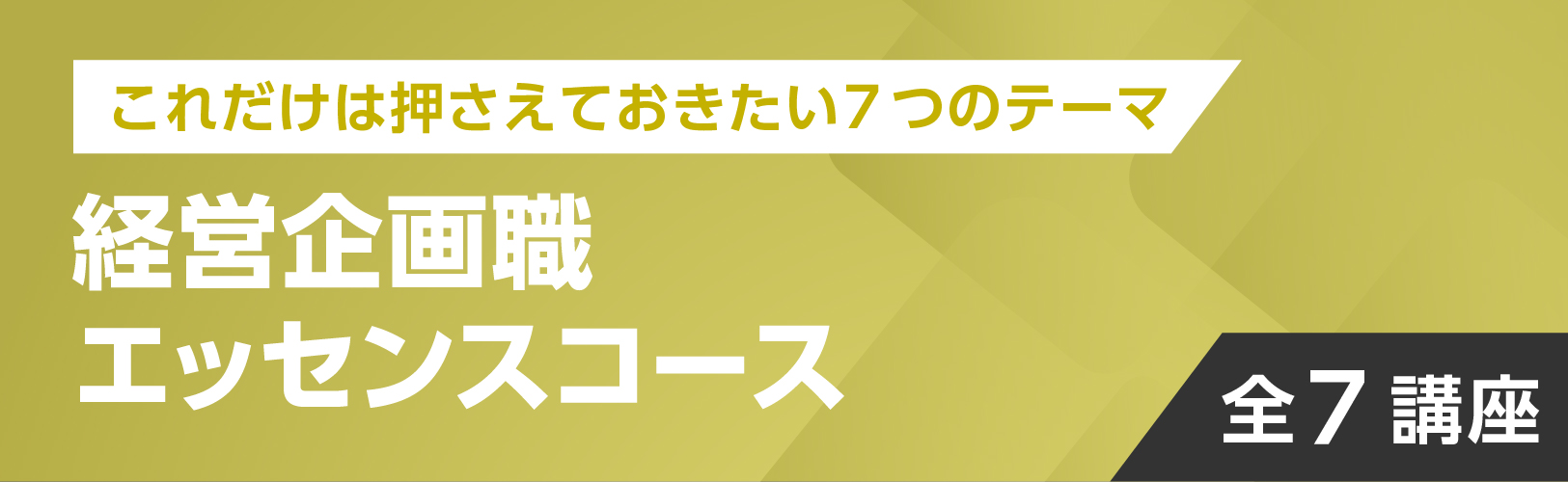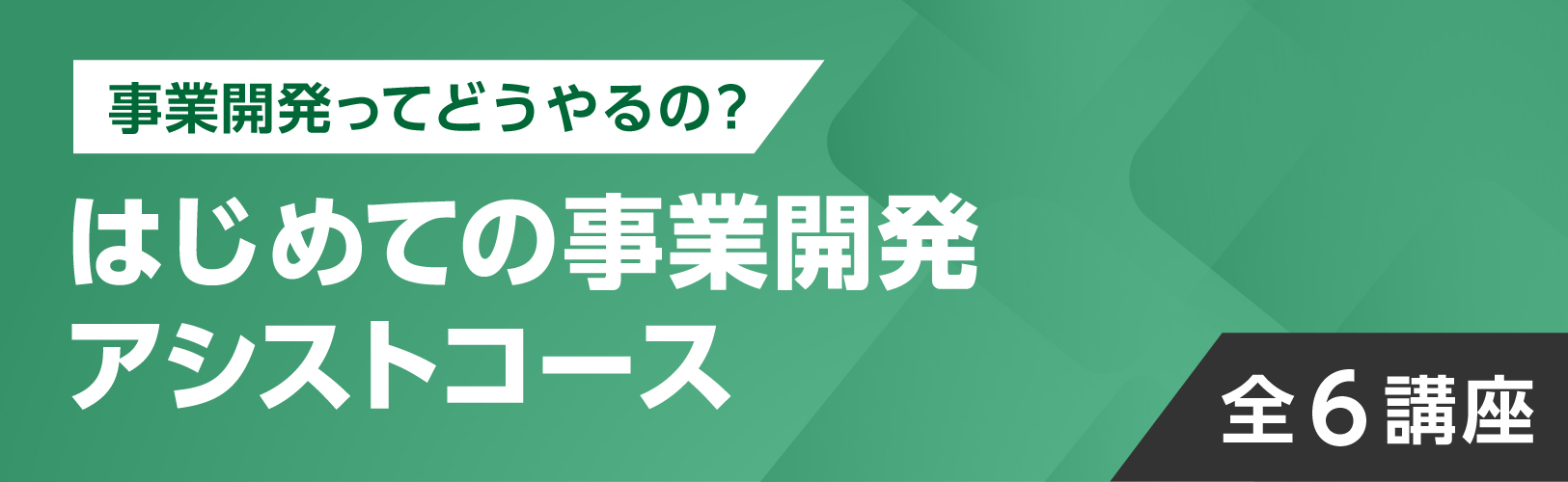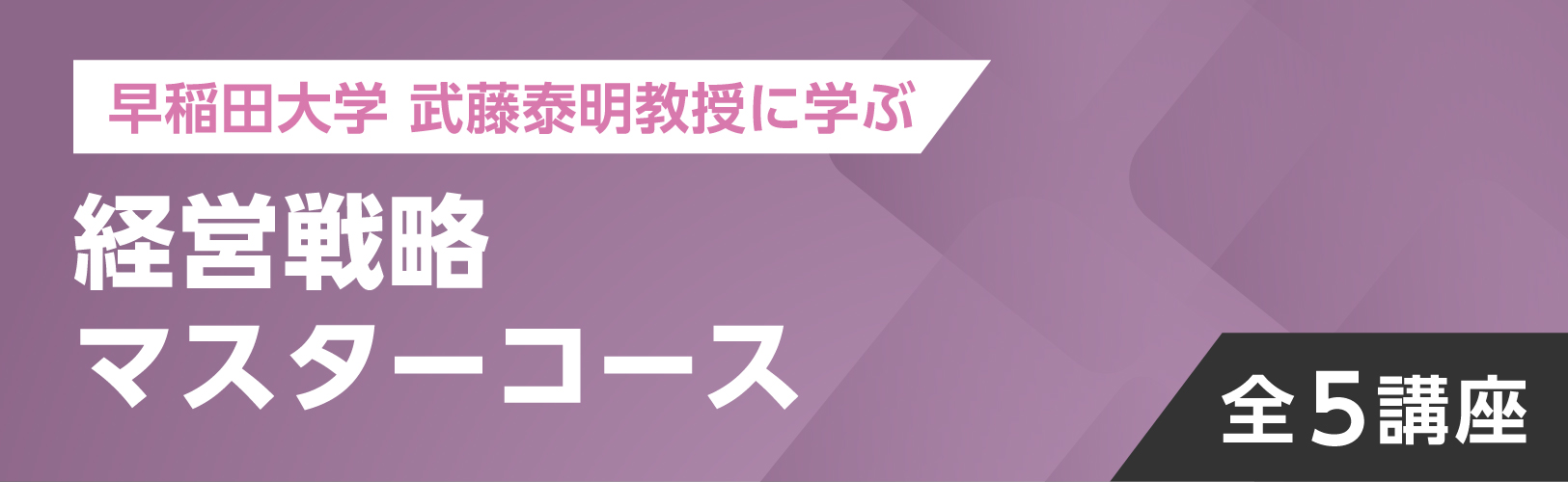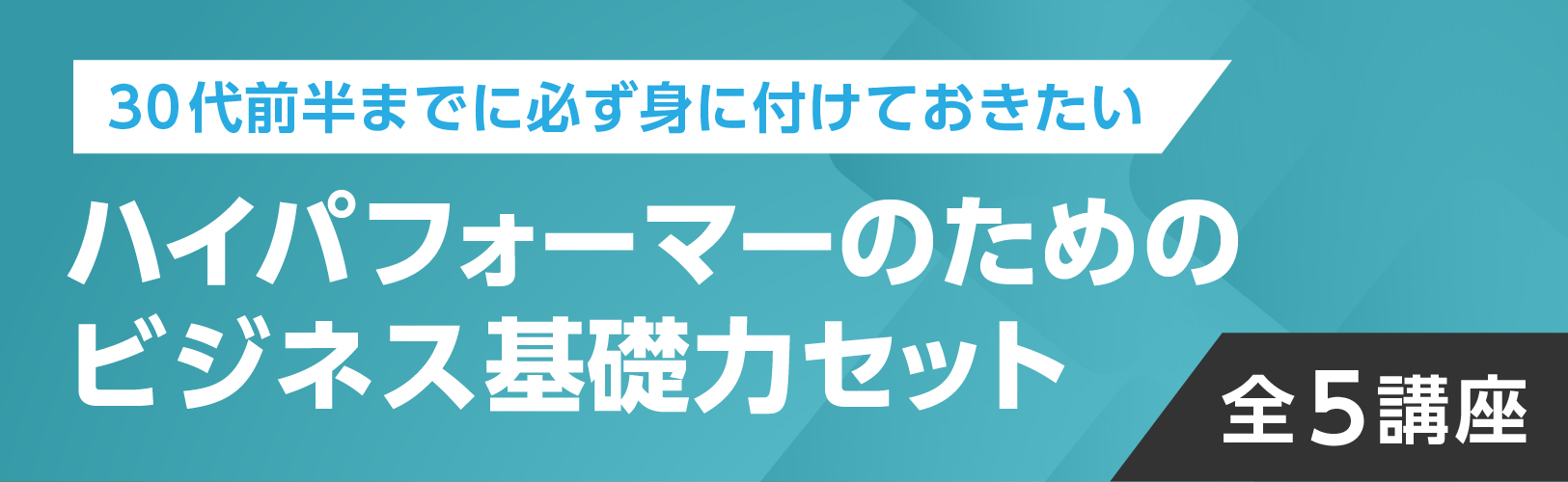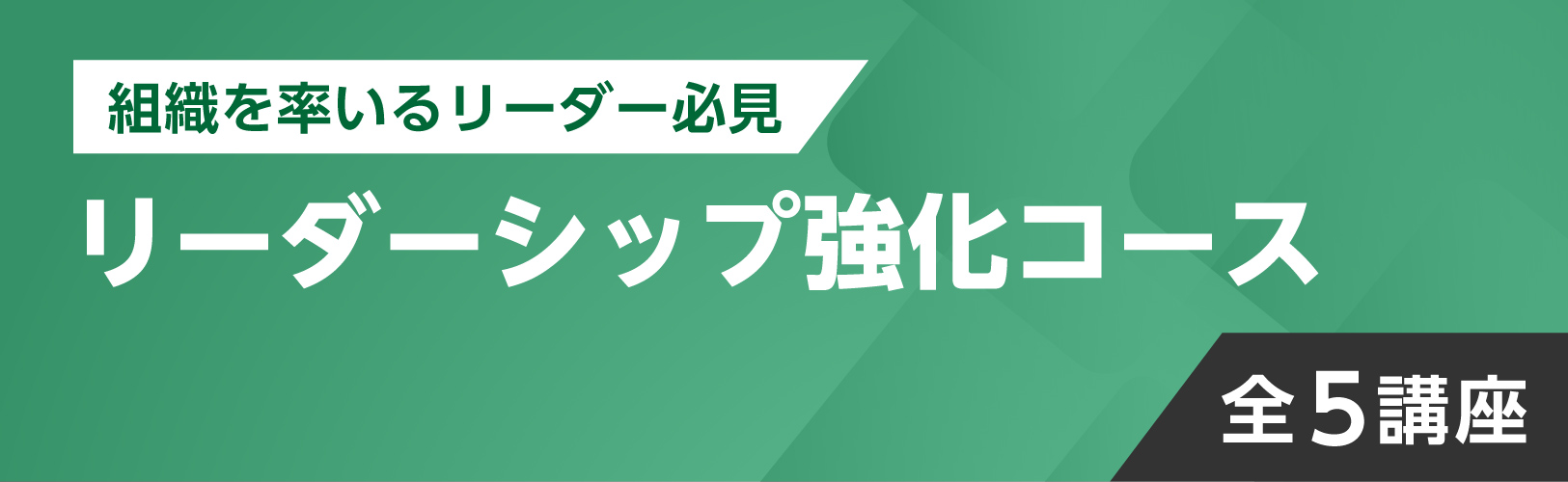日経グループの総力を挙げて、世界に通用する人材の育成の場をご用意します。
講座・コースラインナップ
募集中のビジネス講座
体系的な学びでスキルと自信を手に入れる

技術革新のトレンドや社会の変化、適切な現状認識と関連情報との関係性から未来を見通す。戦略構想や経営判断に必要な事業の未来を読み解き、描く手法を学びます。 .nbss-topic-tbl{width:100%; background-color:#FFFFFF;}.nbss-topic-tbl th{text-align:center;padding:8px;border:1px solid #c
河瀬 誠 他2024年5月15日(水)、5月31日(金)
88,000円

これから10年間にどのような技術が登場し、社会が変化し、産業の姿をどう変えていくか、具体的かつ包括的に俯瞰し、戦略を適応させる道筋を考えます。 本講座はビジネスリーダー向けシリーズ(未来創造リテラシーコース)のひとつです。 企業が未来に向けて存続し成長するためには、未来の事業環境の変化に対応して、自分自身の未来を創造していかなければなりません。 この事業環境の変化を的確にとらえるためには、
河瀬 誠2024年5月15日(水)
44,000円

プロジェクトマネジメント、論理的・戦略的思考、コミュニケーション、リーダーシップなど、いまリーダー、マネジャーに必要なマネジメントの基礎力を体系的に学ぶ 本講座はビジネスリーダーに必要なマネジメントの基礎知識の重要テーマ「事業計画・経営計画・経営管理」「論理的・戦略的思考」「組織・人事・人材マネジメント」を実践的に学んでいただく講座群、マネジメント&リーダー基礎コースのひとつです。 ※「マネジ
西村 克己2024年5月23日(木)
44,000円

現場のリーダー&マネジメント層を対象に、変化する環境下で新しい価値を生む組織や人材を育むマネジメントの考え方と手法を、ポイントを絞り、わかりやすく解説。 本講座はビジネスリーダーに必要なマネジメントの基礎知識の重要テーマ「事業計画・経営計画・経営管理」「論理的・戦略的思考」「組織・人事・人材マネジメント」を実践的に学んでいただく講座群、マネジメント&リーダー基礎コースのひとつです。 ※「マネジメ
寺崎 文勝2024年5月27日(月)
49,500円

事業環境の変化に適応するため、最適な戦略は変わり続けます。戦略の構想→経営計画・事業計画→経営管理と連なる、経営管理の基礎知識と実践ポイントを学びます。 本講座はビジネスリーダーに必要なマネジメントの基礎知識の重要テーマ「事業計画・経営計画・経営管理」「論理的・戦略的思考」「組織・人事・人材マネジメント」を実践的に学んでいただく講座群、マネジメント&リーダー基礎コースのひとつです。 ※「マネジ
武藤 泰明2024年5月24日(金)
44,000円

なぜ今、経営幹部・役員候補者に「学び」が求められているのか? 日本企業の経営は今、かつてない変化に直面しています。気候変動問題をはじめとするサステナビリティ(持続可能性)への対応や、技術やアイデアを生み出す人的資本の確保と投資、アクティビストを含めた多様な投資家との対話など、経営課題は山積しています。しかも、これらの課題に対処を誤れば、会社は深刻なダメージを被りかねません。 経営判断を巡る選択肢
55,000円

「キャッシュがなぜ企業にとって重要なのか」という初歩からわかりやすく解説。簿記や会計の知識が全くない人でも、キャッシュフロー計算書を読み、企業分析に役立てられるよう学習します。.nbss-tm-box.sp-vis .nbss-tm-box{padding:12px 12px;}.nbss-tm-box h3{margin:0 0 0px;font-size:18px;}.nbss-tm-box
南 俊基19,800円

経営者・管理者、人事・労務担当者に必須の労働法、特に人事・賃金制度、休日や労働時間、就業規則、さらに退職や解雇といった人事上の様々な問題に対応するための基礎となる労働基準法を中心に学びます。.nbss-tm-box.sp-vis .nbss-tm-box{padding:12px 12px;}.nbss-tm-box h3{margin:0 0 0px;font-size:22px;}.nbss-
石嵜 信憲 他19,800円

現代企業が求めるマネジメントは「管理」ではありません。経営者の”思い”である戦略を、組織の末端にいる自らの部下に伝え、皆が1つの目標に向かって働いていくようにすることがマネジメントです。
内山 力19,800円
注目の人気講座
著名大学と連携するMBA Essentialsをはじめ
実践力を鍛えるプログラムが多数

競争に勝ち抜く経営戦略とは? 意思決定者の立場で議論を交わす演習型講義で、経営戦略の本質を捉える 不確実性の高い社会の中で激しい競争に勝ち抜くために、個別の事業と企業全体をどのような戦略で成長に導くべきか頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。 本講座は事業単位で考えるべき「事業戦略」と本社レベルで考えるべき「全社戦略」の違いを紐解きながら、ますます複雑・高度化する現代の経営戦略の要諦への理解
淺羽 茂 他2024年5月16日(木)~7月5日(金)
118,800円

未来の金融リーダーを目指すあなたへ。 新たな未来への扉を開く「金融理論とデータ分析能力の基本」を、一橋大学MBAから学びましょう。 日経ビジネススクールは、一橋大学大学院経営管理研究科 金融戦略・経営財務プログラム(HUB-FS)との共同講座を開催します。 金融理論とデータ分析能力のベースを学び、それらの知識をビジネスで活用して意思決定力を高めるための基本を習得できる、一橋MBAカリキュラムのエッ
本多 俊毅 他2024年5月22日(水)~7月3日(水)
69,300円

「MBA Essentials <総合コース>春・秋」は、一流講師陣が指導する早稲田MBA教育を気軽に体感できる、屈指の人気プログラムです。今までのべ12万5千人ものビジネスパーソンの皆様に受講いただき、今年で13年目を迎えます。 5月開講の<総合コース>春と10月開講の<総合コース>秋の年2回のコースで、「経営戦略」「マーケティング」「イノベーション」「ファイナンス」などの全20科目をご用意し
川上 智子 他2024年5月22日(水)~7月24日(水)
66,000円

「MBA Essentials <総合コース>春・秋」は、一流講師陣が指導する早稲田MBA教育を気軽に体感できる、屈指の人気プログラムです。今までのべ12万5千人ものビジネスパーソンの皆様に受講いただき、今年で12年目を迎えます。 5月開講の<総合コース>春と10月開講の<総合コース>秋の年2回のコースで、「経営戦略」「マーケティング」「イノベーション」「ファイナンス」などの全20科目をご用意し
川上 智子 他2024年5月22日(水)~12月10日(火)
132,000円

戦わないで勝てる儲けの仕組みは 「模倣」と「組み合わせ」のビジネスモデル 競争戦略の本質は、長期的な時間幅で「いかにして戦わないようにするか」を考え抜くことにあります。 この発想を突き詰めると、差別化戦略、あるいは市場創造戦略にたどりつきます。ただし大切なのは、差別化を、製品やサービスレベルではなく、生産システム、流通チャネル、顧客リレーションを総合したビジネスモデルのレベルにまで高める必要があり
井上 達彦2024年5月22日(水)~6月19日(水)
66,000円

ビジネスコーチの資格を得て、活躍の幅を広げましょう! 2024年5月18日(土)までのお申し込みで30,000円(税抜)お得です。お早めにどうぞ! お申し込みはこちらまで! 急速かつ激しい事業環境変化を生き抜くには、自ら考えて行動し、成果を生み出すことができる自律的な人材が求められます。対話により思考を高度化し、よりよい行動・成果に導く行為である「ビジネスコーチング」は、自律した人材を育成する
久野 正人2024年6月1日(土)~8月24日(土)
363,000円

ChatGPTって仕事に本当に使えるの? そう思うあなたにぜひ受講いただきたい講座が登場! ◆今まで数日かかっていた資料作成が、圧倒的に効率化する ◆新たなアイデアがどんどん生まれ、企画作成の生産性が上がる ◆相当なコストと時間をかけて行っていたリサーチが、短時間で一定の結果が得られる これらを実現するGhatGPT、みなさんは活用していますか? 躊躇している、使い方がよくわからない、、、と
田尻 望 他2024年6月13日(木)、6月27日(木)、7月11日(木)
79,200円

社会人経験10年~15年程度の方を主な対象にした、リーダーシップとキャリア形成を学ぶ講座。講義やグループディスカッションを通し、業種も職種も異なる受講者同士で切磋琢磨することができます。若手人材の自立的・意欲的な成長の機会として、是非ご活用ください。
八木 洋介 他2024年6月25日(火)~7月31日(水)
330,000円

経営環境の変化が加速する中、世界に比べて周回遅れとの指摘が多いDXの推進は待ったなしです。企業が抱えるさまざまな課題を解決する手段として、デジタルの活用は大きな力を発揮します。 本講座は、世界標準の教育プログラム、教授陣、効果的な学習環境を特徴に持つ名古屋商科大学ビジネススクールの特別プログラムです。デジタル戦略と事業創造の研究に1990年代から取り組んできた第一人者、根来龍之教授と、商社、コ
根来 龍之 他2024年6月26日(水)~8月22日(木)
231,000円

ビジネスと環境・社会貢献の両立を目指し、多様なテーマから持続可能な経営のあり方を学ぶ! 持続可能な世界のあり方を文理融合的な視点から探究し続けている、京都大学の経営管理大学院の知見を基に構成したプログラムです。 21世紀の課題に直面する中、企業は地球温暖化や経済格差への対応が求められています。この講座では、持続可能なビジネスの概念や企業の変革に焦点を当て、従来の経済性にとらわれず、環境や社会への
若林 直樹 他2024年6月27日(木)~8月8日(木)
69,300円

新たな価値を創造するには、「良い問い」が必要だ。 激変し続けるビジネス環境において、「新たな価値創造」や「これまでにない切り口や取り組み」は常に求められています。経営計画にイノベーションや新たな価値創出を掲げ、組織全体で取り組む会社は多く、その一方で担い手不足の悩みも顕著になってきました。イノベーション創出に「向いている人」だけが関われば事足りる状況ではありません。誰もが、イノベーションを創出する
中田 実紀子 他2024年6月28日(金)~7月26日(金)
198,000円

企業や組織の変革をリードするマネジメントを磨く 経済環境が激しく変化していく中、企業や組織が持続的に成長していくためには、柱となる事業の見直しや、成長分野として取り組む事業の組み替えなどを適宜行っていく必要があり、事業環境の変化をとらえて速やかに適応できるマネジメント人材の育成が欠かせません。 「Leading Change Management」は、同校のExecutive MBA*1の基盤
根来 龍之 他2024年8月2日(金)~8月4日(日)
550,000円

「社会問題にビジネスの方法で取り組む」ソーシャルビジネスをはじめ、最新の事例を通じて「社会デザイン」に関わる諸テーマを包括的に学び、さらにワークショップを通じて、ご自身の考えをブラッシュアップしていただきます。講師は、立教大学大学院社会デザイン研究科をはじめ、多様な現場での理論と実践に優れた経験豊富なエキスパートが担当します。
中村 陽一 他2024年7月24日(水)~9月18日(水)
77,000円

「誰に」「何を作って」「どう売るか」を捉えなおす全4回 マーケティングは、ビジネスパーソンの誰もが知っておくべき必須の知識です。基本的なフレームワークや概念は、すでにご存じの方も多いでしょう。 しかし「知っている」だけでは、実務に有効に活かしたり、適切な判断に使えたりできるわけではありません。またデジタル化が進み、ツールや手法があふれ、様々なことができるようになった反面、マーケティングの知見
澁谷 覚2024年7月25日(木)~8月22日(木)
66,000円

経営数字から企業の戦略や経営者の方針を読み解く! 国内外・多業種にわたる事例を通じて、演習形式でスキル習得を目指す 「英語以上のグローバル言語」とも言われ、ビジネスにおける世界共通の言語である会計(アカウンティング)。グローバル化・技術の進展で国際的なM&A等も増える中、客観的な情報をもとに適切な経営判断をしていくためには、「経営にかかわる数字」を読み解く力が欠かせません。 本講座では、財務諸表
西山 茂2024年8月29日(木)~9月19日(木)
66,000円

チームの主体性を高め、人と組織を成長に導きたいビジネスリーダー対象 「ビジネスコーチング」の理論から簡単な実践までを、2日間でコンパクトに学べます! ビジネスコーチングは、ビジネスにおける目標達成と個人の成長を加速するためのコーチングと定義され、人と組織の行動変容を支援するコーチングのことを指します。 リモートワークや在宅勤務の定着、オンラインミーティングの日常化が、ビジネス現場におけるマネジメ
橋場 剛2024年9月3日(火)、9月10日(火)
38,500円

M&A成功へのカギ 企業価値評価の専門知識と実践的スキルを学ぶ 環境が日々変化する今日のビジネスにおいて、M&Aは日本の企業経営において決して他人事ではなく、戦略の一環として注目されています。 企業は新たな成長の機会を求め、M&Aに取り組んでいます。しかし、M&Aに関わる際に多くのリーダーが直面する難題の一つが、企業価値評価の複雑さです。 M&Aが成功するためには企業価値評価が欠かせません。新し
服部 暢達2024年9月3日(火)~9月24日(火)
66,000円

経済価値と社会価値を両立する戦略と実践を学ぶ、 世界最先端のサステナブル・マーケティング! 気候変動や人権問題等の社会問題への関心の高まりとともに、CSR経営、ESG投資が重要課題として注目されるようになり、財務・非財務と分けてとらえられがちだった経済価値と社会価値を同時に追求する戦略が今、必要とされています。 本講座では、マーケティングとイノベーションの最新理論に基づき、地球と社会と企業にとっ
川上 智子2024年9月11日(水)~11月7日(木)
118,800円

行動経済学の世界へようこそ! 行動経済学という言葉を耳にしたことがある方も多いと思います。 コロナ禍で、人々の行動変容を促すために、行動経済学の知見に基づいた取り組みが広く活用されるようになりました。 それ以前からも、行政の現場では、災害時の早期避難や、健康診断の自主的な受診等を促進するためにその知見が活用されていました。 その高い効果に触発されて、行動経済学の知見を行政サービスや組織運営に活用し
大竹 文雄 他2024年10月7日(月)~12月2日(月)
84,700円

ビジネスコーチの資格を得て、活躍の幅を広げましょう! 2024年9月28日(土)までのお申し込みで30,000円(税抜)お得です。お早めにどうぞ! お申し込みはこちらまで! 急速かつ激しい事業環境変化を生き抜くには、自ら考えて行動し、成果を生み出すことができる自律的な人材が求められます。対話により思考を高度化し、よりよい行動・成果に導く行為である「ビジネスコーチング」は、自律した人材を育成する
久野 正人2024年10月12日(土)~12月21日(土)
363,000円

「MBA Essentials <総合コース>春・秋」は、一流講師陣が指導する早稲田MBA教育を気軽に体感できる、屈指の人気プログラムです。今までのべ12万5千人ものビジネスパーソンの皆様に受講いただき、今年で13年目を迎えます。 5月開講の<総合コース>春と10月開講の<総合コース>秋の年2回のコースで、「経営戦略」「マーケティング」「イノベーション」「ファイナンス」などの全20科目をご用意し
池上 重輔 他2024年10月10日(木)~12月10日(火)
66,000円

セキュリティ攻撃は減らせませんが、情報リスクは学習で防げます 実践的なプログラムでビジネスに必須の情報セキュリティをスマホで学びます。
13,200円
グローバルビジネスで通用するスキルを身に付ける
成果につながる世界標準の実践力をいつでも、どこでも
自身のスキルを客観的に見える化する
客観的で信頼性のあるアセスメント
お知らせ
- 2023/05/18
- 【重要】日経ビジネススクールに登壇する講師を名乗って、LINEの投資目的グループに勧誘するウェブサイトの存在が確認されました。弊社ならびに講師は、このようなグループとは一切関係がございません。十分にご注意いただきますようお願いいたします。
- 2022/04/11
- 日経ビジネススクール オンデマンド機能をリリースしました
- 2022/04/11
- 日経ビジネススクールの利用規約を改定しました
- 2018/10/01
- 「日経ビジネススクールにおける個人情報の取扱いについて」を変更しました